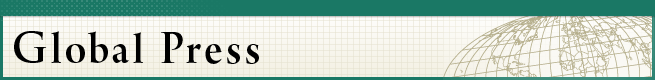http://webronza.asahi.com/global/2011021700001.html
国境を越えた子の連れ去り~オーストラリアの離婚事情と日本のハーグ条約批准問題を考える~
2011年02月21日
妻が子どもを連れて実家に帰る――日本ではそれほど珍しくはないその行為も、ひとたび国境を越えると、「誘拐」と呼ばれる危険性をはらんでいる。実際に、国際刑事警察機構(インターポール)の「ウォンテッド・リスト」には、実子の誘拐罪で国際指名手配されている日本人も何人か含まれている。
国外への“子の連れ去り”は今、グローバルな社会問題として注目されている。

![]() 2008/09年度の連邦家庭裁判所による裁定では、半分以上の時間を過ごすことが母親に認められたケースが59%、父親に認められたケースが18%
2008/09年度の連邦家庭裁判所による裁定では、半分以上の時間を過ごすことが母親に認められたケースが59%、父親に認められたケースが18%
オーストラリアでは、2009年中に国内で登録された婚姻のうち、夫婦のどちらもオーストラリア生まれなのは58%で、残り42%、つまり5組に2組は夫婦の一方、あるいは両方が外国生まれだ。おとぎ話のように「末永く幸せに暮らしましたとさ」となれば、めでたし、めでたし、で終わる話も、現実はそうとは限らない。子どもを支援するための政府機関CSA(Child Support Agency)によると、「結婚の40%が離婚に終わる」という。
離婚カップルの約半数に未成年の子どもがいるが、「離婚は夫婦の別れであって、親子の別れではない」というのが、オーストラリアの大原則。2006年に改正された家族法は、暴力や虐待から保護される必要がない限り、離婚後も父母双方が平等に分担した親責任を持つことが、子どもの最善の利益であるという考えに基づく「共同親責任」が中核を成している。破綻は「終わり」ではなく、新たな親子関係を構築するためのスタート地点なのだ。
この大原則のもと、親が離婚した子どもの大半は「ペアレンティング・プラン」に沿って、片方の親と同居しながら、週末や休暇などにもう一方の親と一緒に過ごすという形で、父母の間を行き来する。それぞれの親と過ごす時間の配分はケース・バイ・ケース。話し合いがうまくいかない場合は裁判に持ち込まれるが、DV(ドメスティック・バイオレンス)の被害者だったり、取り決めに強い不公平感があったり、子どもを失うかもしれないという恐怖心にかられて、などの理由で、時に一方の親が無断で子どもを連れ去る事態も発生する。夫婦の一方あるいは両方が外国生まれの場合は、国外へ逃亡するリスクが高いため、空港や港で照合される「ウォッチリスト」なるものに子どもの名前を載せる手続きをしている父母も決して少なくはない。
連れ去り問題に関する国際ルールとしては、「国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約」(Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction)があり、オーストラリアは1987年に批准している。通称「ハーグ条約」は、一方の親によって他国に連れ去られた16歳未満の子を、それまでの常居所地の国に戻すための国際協力を規定したもので、欧米を中心に82ヵ国が締結国となっている(2011年2月現在)。主な目的は、元いた国へ迅速に子どもを返還するシステムの確立だ。普段誰と暮らし、非同居の親とどのように交流するか、といった子どもをめぐる紛争については、子どもの生活基盤のあった国に持ち帰って解決するのがベスト、というのが基本的な考え方である。
とはいえ、すべての申し立てに対して、自動的に返還命令が下りるわけではない。条約には、重大な危険があると判断された場合などに適用される「例外事由」が設けられているからだ。棄却や取り下げのケースもある。
たとえば、2009年中にオーストラリアからほかのハーグ条約締結国に連れ去られた子95人のうち、返還されたのは68人。反対にほかのハーグ条約締結国からオーストラリアに連れてこられた子は83人で、返還されたのは31人となっている。この年の返還率は前者が72%、後者が37%ということになるが、2008年はそれぞれ41%と70%、2007年は66%と49%なので、かなりバラつきがある。
今のところ、日本はハーグ条約を批准していない。そのことをめぐる風当たりは、このところ強まる一方だ。
「誘拐を容認する国」「拉致大国」といった強い言葉で日本が非難されるのは、度重なる欧米諸国からの早期批准の要請に「検討する」と答えつつも進展がないなか、日本人による連れ去り事件が頻発しているからにほかならない。
日本人同士の婚姻の破綻でも、日本では「先に連れ去った者勝ち」となりがちで、一方的な面会拒否にあって自分の子どもと会えない親がたくさんいることが広く知られるようになり、危機感が募っているのだ。
悩ましいのは、連れ去る側がDVの被害に遭っていたケースが決して少なくはないこと。ただし、それは日本人だけに限った話ではない。
DV被害者の日本人女性やその子どもは、日本に帰ってしまえば安全に暮らせるのかもしれない。しかし、それでは弱者に対する暴力は解決されない。海外で暮らす日本人の中には、DVに遭っても在住国に留まることを決意し、言葉やシステムの壁に阻まれながらも、その国の社会的資源を活用して合法的に戦っている人もいる。
反対に、日本に住んでいて、外国出身の夫または妻に理不尽に日本国外へ子どもを連れ去られた人もいるが、日本がハーグ条約未批准のために、子どもが日本に返還されるよう相手国へ要求することはできない。
日本政府が、「連れ去りの黙認」しかできないとしたら、あまりにも無策で片手落ちではないだろうか。公平かつ実効性のある解決策を模索せずして、いったいどうやって彼らを支援・救済するというのだろう。
日本の批准に関しては、普天間問題で混迷する日米関係を修復するため、次回訪米時に菅首相が加盟方針を表明するという見方も一部メディアで報じられたが、この問題が外交カードとして扱われることには大きな違和感がある。
国内法や慣習との整合性を考えれば、多様化する「家族」に日本が今後どう向き合っていくのか、が問われていることは明らかだ。日本在住の国民にはあまり関係がないと思ったら大間違いなのだ。
離婚後に単独親権となる日本の制度は、果たしてこのままでいいのだろうか。
夫婦関係の破綻により、子どもがいずれか一方の親と会えなくなることはやむをえないことなのだろうか。
子どもにはどちらの親とも会う「権利」があるのではないだろうか。
DVや虐待から子どもを守るためには、具体的にどうすればいいのだろうか。
そういったことを考えるのに、またとない機会なのだ。いかにして公平な仕組みを創り出し、運用をしていくのか、といった本質的な議論と関心の高まりを期待したい。
以前、某国からオーストラリアに移住してきた女性に、「日本人にはいざという時に帰れる国があるものね」と言われたことがある。
平和で安定した祖国があることは、ものすごく幸せなことだ。けれど、逃げ込める自らの祖国があるがゆえに、子どもが慣れ親しんだ在住国のルールにのっとって解決することを放棄し、思いつめたあげくに、心ならずも指名手配されたり、誘拐犯と呼ばれたりする道を選ぶ日本人が少なからずいるのは、皮肉な話だと思う。

- 南田登喜子(みなみだ・ときこ)
- フリーランスライター。オーストラリアを皮切りに、各地で言葉を学び、旅と仕事を交互に繰り返しつつ、7年をかけて五大陸70カ国余りを放浪。世界中にステキな場所がたくさんあることを実感したものの「やっぱりオーストラリア!」と振り出しに戻る。現在はシドニー及びポートスティーブンスを拠点に活動。