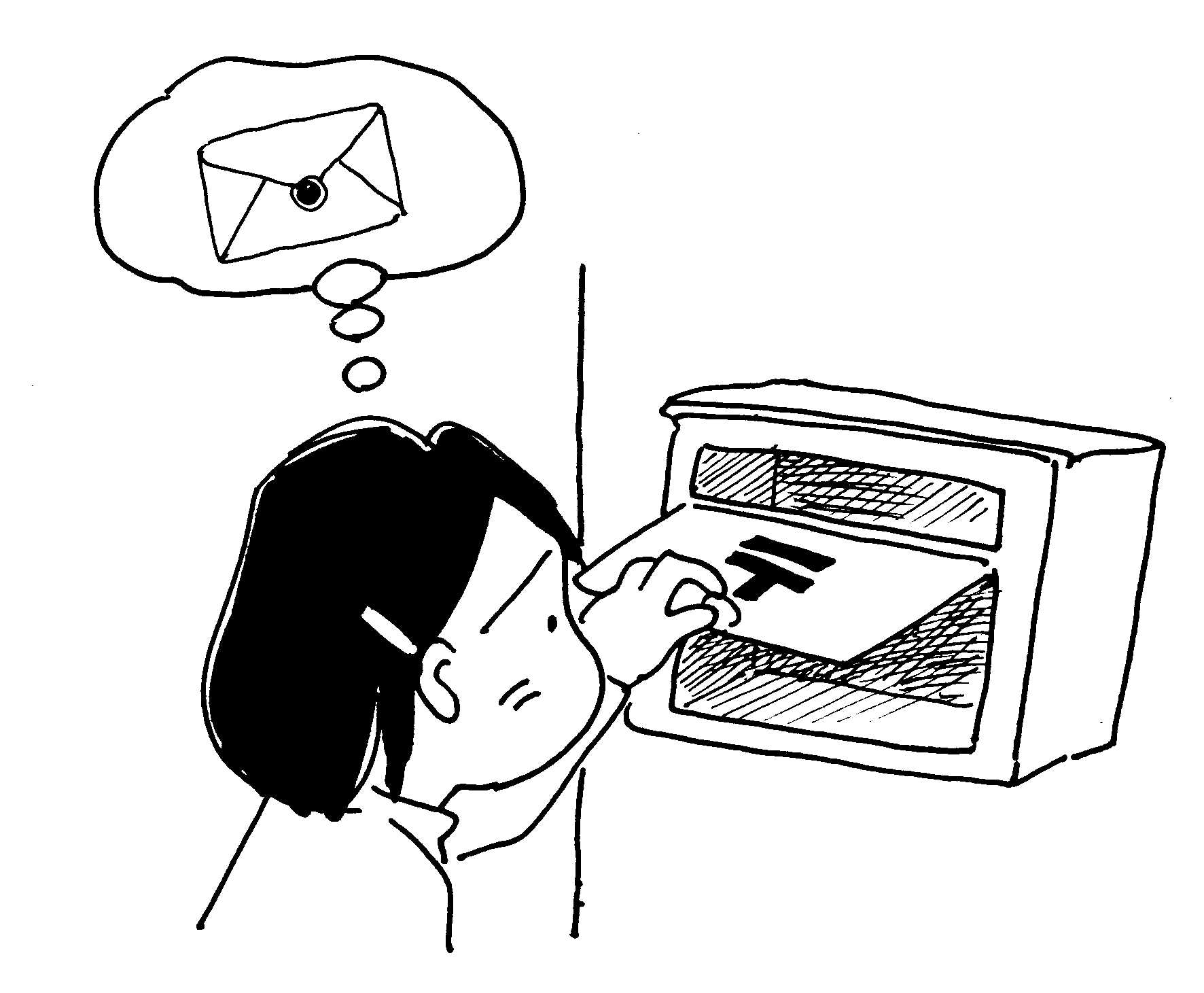https://note.com/drnahomiswan/n/nbf13d1388211
Dr. Nahomi Swan
2021/07/25 08:27
一夜にして悪人と善人が逆転した。祖母の呪文から、母の心理的圧迫から、「殉教者の娘としての罪悪感」(信田、2018)から、「毒親」(スーザーン・フォワード著、羽田詩津子訳、『毒親の棄て方ー娘のための自信回復マニュアル』、新潮社、2020年出版)の縛りから、一気に解放された瞬間を味わった。夢の中で、門番である祖母がやっと死に絶え、監禁状態から抜け出すことができた。母に乗せられたコーヒーカップの中でぐるぐる回り続け、路頭に迷った半世紀の旅が終焉した。今まで想像しなかった、突如古いものが大波で流され、その勢いで新天地へ導かれるような人生の大展開に遭遇するような気持ちだった。すぐに父に会って抱きしめてもらいたいと思ったが、父も死ぬほど会いたけれど心の準備が必要だと言い、私たちは一年間ほど書面のやりとりをしてから再会を実現した。その後も父と娘の関係を超えたソウルフレンドのような不思議な関係を保ちながら、書簡を通し秘密のやり取りを続けている。父と繋がってから気づき、非常に驚いたことがあった。それは私は父の母校で教壇に立っていたということである。それを知らずに、日本に戻った際、その教育機関の公募を受け教職についていた。父は私が博士となって父の母校で教員をしているということを大変喜んでくれた。私が母から批判され、軽視されてきた側面を父から認めてもらえたことが何より嬉しかった。父を知れば知るほど、私が理想としてきた父親像であると納得できた。この人に会うために私は今まで生きてきたのではないかと思うぐらい理想の父で、私の心の中の父性を探す長旅の終着点にやっと辿り着けたと感じている。私と姉はいつも父の心の中にあったと父は言ったが、姉に関してはわからないが、私についていえば、それは本当であったと思う。
父はまるで「アニムス(内的男性性)」のような存在で、いつも父と私は内的世界の中で繋がっていたと私の半世紀の心の旅を回顧する時、実感できる。3年前に自宅の戸口で見た老人が父ではなかったかと思い、本人に尋ねたところ、半世紀間一度も出身地へ戻ったことがないというので大変驚いた。あの老人は、夢や幻であったのだろうが、ユング心理学的に言えば「ビジョン」である。3回目のビジョンを見た時、私の心の中に「アニムス(内的男性性)」という言葉が浮かんだ。そのビジョンは3回の中で少しずつ変容していった。1回目は空白(覗き窓の外を確かめに行かなかっため)、2回目は男になったような母の姿、3回目は父の姿であった。2回目の人物が英語を話していたことは興味深い。私にとって英語は、象徴的な意味で、新しいアイデンティティを与えてくれた未来の世界との媒介言語で、父と私が理解でき、母が理解できない言葉なのである。男のような母の姿は「父と母の二人分頑張るお母さんだから、性格がきつくても許してあげてね。」と祖母に言われた母のイメージを思い出す。この3つのビジョンは、私のアニムスの成長的段階を示しているように感じる。2回目と3回目のアニムスの違いは、ユングに従えば、「否定的アニムス」あるいは「アニムスに取り憑かれた女性」VS「肯定的アニムス」(ウェーア, 1987)と言えるかもしれない。しかし、ユング派のフェミニストである私は『ユングとフェミニズムー解放の元型』(1987)の著者デマリス・S・ウェーア(1987)の以下の主張に賛同し、「アニムス」(内的男性性)や「アニマ」(内的女性性)や「影」(無意識の中に潜在する抑圧された誇れない自分の部分)といった「元型」(集合的無意識の内容を表す共通したパターン)を静止した本質的なものとして捉えるのではなく、私たちの経験と視点で日々解放されるべき対象であると理解する努力を忘れないようにしたいと考える。「ユングが体験的なものや非合理的なものだけでなく、わたしたちの最も深い霊的問題の現実をも強調したことは、西洋社会の物質主義是正に向けての一つの顕著な動きである。女性的なるものを正当に評価しようというユングの努力の中にさえ含まれているのだが、女性たちと女性なるものへの恐れをただすことは、ユングの心理学をホーリスティックな心理学と霊性にするうえでどうしても欠かすわけにはゆかない一歩であろう。女性たちはユングの心理学がそのように発展することを必要としているのである」(p. 163)。
母があの時父との復縁を受け入れていてくれたなら、私は母を置いてわざわざ海外へ心の中の父性を探す旅には出なかっただろうにと思うと、母の決断が愚かに思えて仕方がない。しかし、逆に、もし父が私が高校生の時に家に戻ってきてくれたなら、私はここまで頑張ることはなかっただろうし、今の最愛の夫とも一緒になることができなかった。何よりも、私が50代の心理専門家であったからこそ、傷ついた父の心の癒しの手伝いをしながら、新たな父と娘の関係を築き始めることができたように感じるため、やはり、悔しいと思う反面、これが運命だったのだろうと納得できてしまう。
とはいえ、この私の父に纏わる体験談は素敵な父に会えてよかったという甘いハッピーエンドの物語ではなく、一年かけて少しずつ癒されてはきたものの、非常に苦痛な心理状態を味わされる毎日なのである。まず母への怒りの気持ちをうまく対処することができない。母も一人の女性としての人生があるのだから、母の決断と母が歩んだ人生について私がどうこう言えるものではないとは頭で理解している。しかし、母のロマンスを家庭よりも第一に選ぶという決断のために、父も、私も、周囲の人々も苦しむ結果になってしまったことは遺憾だ。母自身も華やかな水商売の世界から老後の一人の生活に変化し寂しさを味わう中、もしかしたら、あの時父と復縁をしていればよかったと後悔しているかもしれない。当時は母も極限の中でベストの決断をするしかなかったのであろうし、父なき子にされた私のために精一杯、お金や物を与えようと尽くしてくれたことには感謝しなければならないと思っている。しかし、ブランドのバッグも衣類も美味しい食べ物も、父親の代わりにはならなかった。私の心を満たしてはくれなかったのだ。この気持ちは、まるで誤診によって間違った処方箋を受け取り、効かない薬をずっと飲み続け、副作用に悩んできたような感触である。私としてはあの時戸籍上父の娘になれなかったとしても、一目でもいいから会わせて欲しかったのだ。「あなたのお父さんはこんなに頑張ったよ。あなたのことを一度も忘れていなかったよ。こんなに立派になって帰ってきてくれたよ。」と言って紹介して欲しかった。そうすれば私は家を遠く離れることはなかった。母は私を失わずに済んだだろう。一年に一度でいいから父に会えていたら、どんなに良かったかと思う。喫茶店で2時間一緒にコーヒーを飲みながら過ごすだけでもいい。政治、経済、社会問題について語り合い、生きる哲学を教えて欲しかった。そんな風な関係があれば、私の鬱病は酷くはならなかったであろうし、精神的にバランスの取れた人間となり、母が困るぐらい新宗教に没頭しすぎることもなかったはずだ。しかし、母は私が育っていく中で、性格や考え方が父に似ていることに気づき、もし父の真相がわかれば、私は父の元へ絶対に行ってしまうだろうと恐れ、必死に父の存在を隠すことしかできなかったのだろうと思う。
母が父の送金のことなどを隠し切っていたのは、私にだけでなく祖父母や親戚に対しても同様だった。なので、父はいまだに皆にとって「悪い人」のままになっている。今までずっと私を愛し私のために懸命に生きて存在していた人が悪い人にされ、いないも同然とされてきたのである。これはまるで人殺しだ。これほどの人権侵害があって良いのだろうか。そして母や祖母は知らないのだ。「悪い人、いない人」という父へ向けられた矛先は私の胸にもしっかりと突き刺さっていたことを。私は父の子として出自について真実を知る権利がある。父を批判し否定し、真実をあやふやにしたことによって私のアイデンティティの半分が批判され否定され、あやふやなものとされたのである。私は心理士として離婚後傷ついた多くの子供たちの心理アセスメントやカウンセリングを行なってきたが、別居親の存在を否定された子供たちが絵画で自身を表現する時、半分が真っ黒になっていたりするのを見てきた。又、暴力団員の父であっても子供は父が恋しく面会交流を楽しみに生活しているという事例なども対応してきたし、殺人犯の親についても、あからさまに「悪い人」として面会交流を遮断するのではなく、子供に分かる言葉で適切に説明し徹底した配慮の下、面会交流をするという事例なども欧米の同業者の友人から聞いて学んできた。祖母が父について語る時しきりに使っていたこの「悪い人」という言葉は、単純なだけに恐ろしい。私が信じていた宗教の布教師である祖母が使った言葉であったからこそ、私は50代になるまで信じて疑うことがなかったのだ。心理職の専門家として経験を積めば積むほど、人間とは複雑な生き物であるということを実感するが、その人間たちを「悪い人」と「良い人」の二つに振り分けてしまうことなどできないと痛感している。そう言いつつも、今、私の中では、同居家族=良い人たち VS 別居家族(父)=悪い人が一気に逆転してしまい、心の中で母や祖母が「悪い人たち」になってしまっており、この気持ちに折り合いをつけるには相当な時間を要すると感じ、自身の教育分析やカウンセリングを継続している状態だ。
今私にとってトラウマのキーワードになっているのは「日本の女子高校生」である。自分の高校時代のことを思い出したり、女子高校生に纏わる話を見聞きするだけで胸が苦しくなるのだ。最近、又海外へ戻ってきたが、日本にいる時は街中で女子高生の姿を見かけるだけで涙が溢れ出てきた。この年代の頃、私が夢見ていた父と母のいる普通の家庭の幸せが得られる一歩手前にいたのかもしれないと思うと大変切なく、槍で胸が突き刺されそうな気持ちになり、胸を手で押さえながら歩く時もあった。まるで、戦国時代にお家騒動で親子断絶となった武士の娘のような気持ちなのである。私はそんな時考えた。なぜ実子の私が実父の実母との復縁の意思を全く聞かされなかったのか。これは私の子供の人権が侵害されたことを意味するのではないか。なぜ、あの時の私の子供としての人権を日本の大人たちは誰も守ってくれなかったのか。私たちの日本という国は民主主義国家ではなかったのか。民主主義では人権が守られるべきではないのか。50歳を過ぎてもこんなに辛いのだ。もう少し若ければ私は耐えられず、怒りの矛先を母に向け、若気の至りで母に危害を加えるようなことになっていたかも知れないと思うとぞっとする。このような私が体験する親子生き別れの悲劇は単独親権社会日本の中で今も続いている。50代の心理専門家の私でさえこんなに苦しく行き場がない思いに駆られているのだ。私のような状況の只中にある犠牲者の子供たちのことを考えると胸が痛んで仕方がない。
カウンセリングを受けながらも、母に対する怒りの処理がどうしてもうまくいかず困り果てた時、私は一つの儀式を行なった。親不孝と思いながら、母からもらったものを全て処分したのだ。母が買ってくれた洋服やアクセサリーを身につけているだけで窒息死しそうな気持ちになり前へ一歩も進めないと思ったためだ。父が家を出て行った時、父の所有物を全て燃やし死んだ人としたと聞いたことがあったので、これは私の中での小さな仕返しだった。その儀式後、もし父が高校生の時私の父となってくれたなら、きっとこんな物を買ってくれたのではないかなあと思うものを見つけ、父からの自分へのプレゼントと見なし、どんどん購入した。愚かだと思いながら、そんなことしか成す術を知らなかった。そして、段々に私の異母姉妹の妹が羨ましくて仕方なくなった。彼女が得られた幸せを後一歩で私も得ることができたのにと思うと悔しくて涙が流れた。その度、母の決断を恨む気持ちが強くなり、一層母への憎悪が高まった。ただ一つだけ、母との関係の中で新しい良い気づきがあった。それは、失敗をした時など幼少の頃の母との苦しい思い出が心に浮かび、一層落ち込み始めることがあるのだが、父と繋がる前は、そのような時は「私さえ死ねばいいのに」という希死念慮が浮かんでいたのだが、父と母についての真相が分かってからは「この女のために私が死んでたまるか。」という強い生きる意思の声が心の中に響き渡るようになったのだ。これは私にとって大きな心の収穫であるが、ユング心理学の「影」という存在が今までうっすらとぼやけていたのがはっきりと浮き彫りにされたからではないかと考えている。
今回の父との繋がりについて、以前のまま父の真相について何も知らない方が良かったのかもしれないと思うほどの心痛を抱えているが、結果的には知ることができて良かったと思っている。この体験は私が今後も心理士として成長するための教育分析のために、心の試練のために必要であったと思うからだ。自分でもなぜか判らないほど高校生の後半ごろから母が嫌で仕方なかったが、私の知らないところでこんなやり取りが父との間にあったのだと分かると、私の内的世界が何かを察知して、母との関係がギクシャクする結果を招いたいのではないかと憶測し、納得できる。母に対する怒りはどうしようもないものがあるが、キリスト教の信仰やカウンセリング以上に私を癒してくれたことがあった。それは、共同親権社会運動との出会いであった。当事者の方達と共に単独親権社会の仕組みや思想を学ぶ中、母も、娘を父なき子にするか自分の幸せを取るかという二者択一の決断を迫られ、苦渋の選択をしなければならなかった一人の犠牲者であったと思う時、哀れな人と思えることでき、少しだけ怒りの気持ちが軽減するのだ。父の手紙を捨て切れなかったところにも母の葛藤や苦しみが感じられ、母の考えは理解できなくても、その辛さを少しだけ垣間見れるような気持ちになるのだ。
それにしても半世紀の家族の真相がはっきり聞かされてこなかったことによって同居家族に裏切られたような気持ちになったことは想像以上に苦しい。棄てられていたということと棄てられていなかったということの事実の違いは大きすぎる。半世紀も「棄てられた娘」というアイデンティティの服を身につけさせられ生きてきたのだ。これまでの私は一体何者だったのだろうかと自分の存在意義や生き方そのものを考え直さなければならないほど深刻な事態と受け止めている。しかし、今や人生100年時代である。私は今後、100歳まで生きて、これからの半世紀を「棄てられていなかった娘」として生き直す覚悟でいる。父は私が半世紀後に連絡を取り、父の心を癒すことができたため、世界一のカウンセラーだと言ってくれた。私はこの褒め言葉を胸に、自分が負った心の傷が無駄にならないように、今後も親の離婚や「片親疎外」に影響された子供たちの心のケアを行なうことができる心理専門家として成長し続けたいと思っている。家庭裁判所調査官小澤真嗣氏(2002)は、「片親疎外」の子供たちの心理について下記のように述べている。「一方の親が面会交流の重要性を理解せず、利己的な判断により、面会交流を妨害、実施しない場合、子の精神状態は、以下のような重大な影響を被る。①拒絶のプロセスに巻き込まれた子どもは、別居親との関係が失われる結果、同居親の価値観のみを取り入れ、偏った見方をするようになる、②同居親が子どものロールモデルとなる結果、子どもは自分の要求を満たすために、他人を操作することを学習してしまい、他人と親密な関係を築くことに困難が生じる、③子どもは完全な善人(同居親)である自分と完全な悪人(別居親)の子どもである自分という二つのアイデンティティを持つことになるが、このような極端なアイデンティティを統合することは容易なことでななく、結局、自己イメージの混乱や低下につながってしまうことが多い、④成長するにつれて物事がわかってくると、自分と別居親との関係を妨害してきた同居親に対し怒りの気持ちを抱いたり、別居親を拒絶していたことに対して罪悪感や自責の念が生じたりすることがあり、その結果、抑うつ、退行、アイデンティティの混乱、理想化された幻の親を作りたすといった悪影響が生じる」(小田切紀子著「序章子ども中心の面会交流に向けて 小田切紀子・町田隆司(編)『離婚と面会交流−子どもに寄りそう制度と支援』 金剛出版, pp.v-xvi. 2020年出版)。全くもって私の体験と一致するため驚愕している。「片親疎外」という言葉さえ知らずに、多くの子供たちの心理支援を行なってきた専門家としての自分を情けなくさえ思うが、今後は、自分の体験を活かしたより良い支援ができるという思いの下、意を新たにしている。
最近私は、夫と共にマイホームのある夫の母国へ戻ってきた。あのまま日本に暮らし、日本の女子高生たちの姿を毎日街で見かけては泣き、母への強い憎悪を心に抱きつつ仮面の笑顔で接し続けることに限界を感じたためだった。以前と同じように、母とは距離を置いて何とか上手くやっていくことができている。母と姉の姉妹のような関係と姉の母への献身的な労りのおかげと感謝せざるを得ない。単独親権社会の下で私たち当事者の家族が味わったような苦しみを未来の日本の家族・子供たちが繰り返し味わうことがないように、日本に共同親権社会が実現する日が一日も早く来ることを願う。
父と繋がってから幾つかの印象的な夢を見てきたが、一番心に残っている夢が一つある。母のスナックが壁のないオープンスペースになっており、宇宙船のように見える。厨房の中の真ん中に母がおり、私は母の左横にいる。大学生の時のように私はカラオケの設定の係をしている。母は店主として客を迎える位置にある。父が入ってくる。父が半世紀後私たちを訪れた。父は私と母を知っている。私も父を知っている。しかし、母は父を知らない。いや覚えていない。父がカウンターの真ん中の席に座り、二人が向き合った途端、母が急にパタンと倒れて死んだ。その後母の葬式があったが、母はみすぼらしい赤い籠の中に入れられていた。この籠は遺体とともに火葬炉に入るのではなく、火葬炉まで運ぶだけの役割をする。この夢について、ドリームワークのセラピストとプロセスワークをした。そのセラピーの中で父のイメージは私に語った。「私は家に帰ってきた。あなたに会うために帰ってきた。私が帰れば彼女は死ぬと分かっていた。しかし私は帰ってきた。彼女が死んだ。だから私は今、あなたと話をすることができる。強く雄々しくありなさい。これまで私はずっとあなたと一緒だった。これからもずっと一緒だ。あなたはとても大切な人だ。あなたの時がやっと来たのだ。自分を誇りに思いなさい。強く雄々しく生きなさい。」私はこれを「アニムス」の言葉と象徴的に受け止めている。私はこれから「アニムス」と共にスナックから変容した宇宙船に乗って心の旅を続けるのだ。
私の内的世界の中で、「影」の象徴である母が死に、「アニムス」の象徴である父が戻ってきた。父母、祖父母、姉は、そういう名前がついているだけで、究極的には、父母でも祖父母でも姉でもない。いくら血縁の関係があっても、大切な何かを私に伝えるために、そのような名前を持って私の前に現れただけの存在である、と私は思っている。家族という人間関係のしがらみに苦しむ時、その関係を本質的ではなく、象徴的に捉えた時、心が楽になり励まされることを私の家族から教わった。母の遺体が納められた赤いみすぼらしい籠は、ドリームワークのプロセスワークで私自身であることが分かった。多くの人間の「影」を「contain(受容し)」、癒す、自らも傷ついた「cotainer (容器)」である私、「傷ついた癒し人」(H .J.M.ナウエン著、西垣二一・岸本和世訳、『傷ついた癒し人』、日本キリスト教団出版局、2016出版)だ。「あなたを父親のない子にしたのは私だから、この罪だけはどんなに償っても償いきれない。」と私に語りかけながら、娘の幸せよりも自分の幸せを選んだ暗闇と苦しみの只中にある「影」という名の実母を赦すことができないまま、傷つけられながら、もがきながら、弱さと限界の中で、私は、今日も「傷ついた」心理士、執筆家として生きていこうと思う。(終わり)
HP: https://drnahomiswan.wixsite.com/my-site-1
Email: drnahomiswan@gmail.com