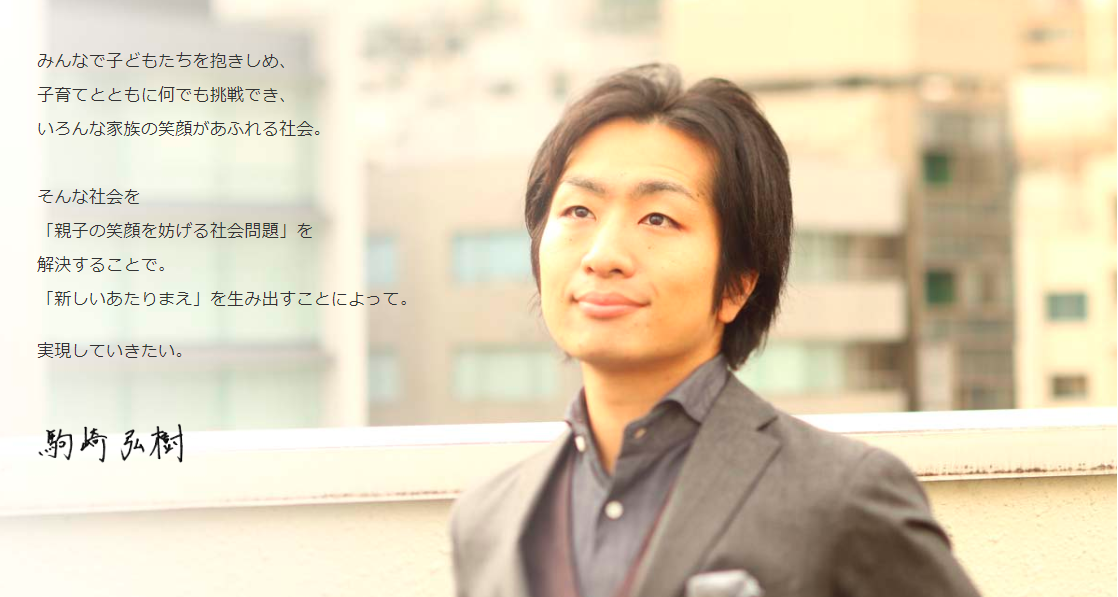https://hanada-plus.jp/articles/323
「10年前の今日(5月6日)、娘が誘拐された――。2歳だった娘は、いまや中学生である」。突然、愛するわが子を奪われた父親(A氏)。彼の身に、いったい、なにが起きたのか。その背後には、連れ去り勝ち、虚偽のDVなど「実子誘拐」の方法を指南する人権派弁護士らの暗躍があった――。愛する娘を奪われた父親が、魂の告発!日本で日常的に行われている「実子誘拐ビジネス」の闇に迫る!
目次
人権派「39人」による集団リンチ
仕事に疲れて家に帰ると、子どもが「おかえり!」と駆け寄って抱きついてくる。ぎゅっとしがみつく小さな手。この子がいるからがんばれる。そんな日常のしあわせが突然奪われる。家に帰ったら、誰もいない。家具もなにもなく、もぬけの殻。
このような子どもの連れ去りが、国内で数多く発生している。子どもを連れ去る者は、なんと一方の親(多くは母親)である。欧米などの先進国の大半では、これは誘拐罪に該当する重罪である。
しかし日本においては、「実子誘拐」は罪に問われず、弁護士らの指導により日常的に行われている。突然愛するわが子を奪われ、子どもに会えなくなり、養育費だけを支払い続けることで、精神的、経済的に追い込まれ、自殺する親(多くは父親)もあとを絶たない。
そのような「実子誘拐」の被害者である父親のA氏が、自身の離婚訴訟に関連し、「妻に暴力をふるうDV夫に仕立て上げられ、名誉を傷つけられた」として、弁護士ら39人を相手に民事訴訟を起こした。被告には、元裁判官を含む弁護士らのほか、NPO法人代表、大学教授、朝日新聞論壇委員(当時)など錚々たる者が並ぶ。
訴状には、彼らの行った名誉毀損行為が「通常の名誉毀損とは全く異質の組織的・計画的犯行」であり、「その精神的苦痛や経済的損失がどれ程甚大なものかは、裁判官自らが一個人として同様の集団リンチを受けたらどうかと考えれば、容易に想像ができるはず」との記載がある。
たしかに、離婚訴訟が単なる夫婦喧嘩が拡大したものでしかないのであれば、夫婦喧嘩の一方の側に39人もの人間が加担し、もう一方の側に対し、集団で名誉毀損行為をすることの意味を成さない。しかも、39人の大半にA氏は会ったこともなく、全く面識もない。
では、なぜA氏は面識もない弁護士や元裁判官ら39人に集団リンチを受ける羽目に陥ったのか。それは、いわゆる離婚ビジネスを生業とする弁護士らの虎の尾を踏んだからである。
被告に名を連ねる39人は、職業も所属する組織も様々であり、一見、それぞれ何も関係なさそうに見える。しかし、訴状には「被告らに共通する点は、欧米諸国では誘拐罪が適用される犯罪行為である親による子の連れ去りや国連児童の権利条約に明確に違反する親子の引き離し行為に関与し、当該行為が引き続き日本で行えることを願う者らである」とある。
この訴状には、A氏の妻(当時)が起点となり、それぞれの被告とメールでやり取りを行っている共謀の証拠も添付されている。
A氏のケースには、家族を崩壊させ、小さな子どもの心を傷つけ、一方の親を追い込む「実子誘拐」の問題点が凝縮されており、このケースを詳細に見ることで、その背後にある「実子誘拐ビジネス」で蠢く集団の実態が見えてくる。
集団の中心にいる裁判官と弁護士は、一般的にどのように「実子誘拐」にかかわっているのか。
弁護士が「実子誘拐」の方法を指南
裁判官は、後述するように「継続性の原則」に基づき、「実子誘拐」をした親に親権を与える判決を下すのが常である。そこで弁護士は、親権を確実に奪うために、離婚を考えている親に対し「実子誘拐」を勧め、方法を指南する。これは憶測で言っているのではない。数多くの証拠がある。
ある女性誌には、弁護士が「親権争いは最初の対応が肝心。家を出る場合は必ず子供を連れて出ること」と堂々と書いている。
日弁連法務研究財団発行の本のなかでは、冒頭に「実務家である弁護士にとって、親権をめぐる争いのある離婚事件で、常識といってよい認識がある。それは、親権者の指定を受けようとすれば、まず、子どもを依頼者のもとに確保するということである」と記載されている。
弁護士が一方の親に子どもを誘拐するよう唆し、裁判を提起させれば、裁判官が親権をご褒美として与える段取りとなっている。
そして、もう一方の親から奪い取った子どもの養育費などの一部をピンハネして弁護士が懐に入れるのである。そのお礼として、裁判官が退官したら弁護士事務所で雇うケースも少なくない。
からくりは極めてシンプルであるが、多くの人はそれに気が付かない。弱者の味方を標榜する弁護士と公明正大であるはずの裁判官がそのような形で癒着しているとは、夢にも思わないからである。
しかし、裁判所の実態は多くの人が想像するものとは全く異なる。国会の審議でも取り上げられた有名な裁判所職員のブログがある。そこには、子どもを誘拐された親を嘲笑し、「自分の要望が通らないからといって自殺を図ろうとする当事者。自分の要望が通らない=裁判所が相手の味方をしていると完全に妄想中。もうだめだと窓から飛び降りようとしたりして本当に迷惑だ。裁判所でやられると後始末が大変だからやめてくれ、ああ、敷地の外ならいつでもどうぞwww」などと記載されている。
妄想でも何でもない。
これが裁判所の現実である。子どもを誘拐され、離婚訴訟を配偶者から訴えられれば、このような司法の闇が待っているのである。
A氏はわが子との生活を取り戻すため、弁護士の常識であるところの「実子誘拐ビジネス」の闇に切り込んだ。そこで、弁護士や裁判官らにより徹底的に社会的に抹殺されかかったのである。
「連れ去り勝ち」の無法地帯
離婚時の親権をめぐっては、松戸判決と呼ばれる重要な裁判がある。
A氏は実は、この松戸判決の当事者だ。2歳で連れ去られた娘の親権をめぐり、2016年3月の一審判決では「自分が親権者となった場合に母親である妻に年間100日程度娘と面会させることを約束し、それを自らが破った場合には親権を妻に渡す」ことを提案したA氏を親権者として相応しいと判断し、A氏に親権を認めた。
それまでの裁判所の先例では、面会交流は月に1回数時間、監視付きが相場で、親権者を認める際には「継続性の原則」という慣例により、同居している親を優先していた。
そのなかで松戸判決は、子どもが両親の愛情を受けて健全に成長することを可能とするため、「より寛容な親」を優先する「フレンドリーペアレント・ルール」を採用した画期的な判決として注目された。大岡越前の「子争い」を彷彿とさせる名判決として、多くのメディアが評価していたものである。
しかし、2017年1月の二審東京高裁判決では一審判決を覆した。
裁判官は「実子連れ去りをした親に親権を与える判決を下す」と述べたが、そのような判決を下すために必要な理屈が、悪名の高い「継続性の原則」である。
この原則に基づくと、一方の親を欺き留守中に子どもを誘拐し、その後、子どもともう一方の親との接触を徹底的に断ち切った親が親権者として認められることになる。この原則は、法律上どこにも根拠はない単なる裁判所の慣例である。
むしろ、「連れ去り勝ち」を生むものであり、他の先進国でこのような子どもの利益に反する慣例を裁判所で採用している国は皆無である。
二審東京高裁判決で裁判官は、継続性の原則を採用したうえで「フレンドリーペアレント・ルール」を明確に否定し、A氏の妻を娘の親権者とする判断を下した。判決文には「親子の面会の重要性は高くない。年間100日の面会は近所の友達との交流などに支障が生ずるおそれがあり、子の利益になるとは限らない」との記載がある。
同年7月、最高裁はA氏側の上告を不受理とし、確定となった。本来、一審と二審とで法律判断が分かれた場合、最高裁は受理し、審議しなければならない。しかし、最高裁は不受理を決定し、審議すら拒否した。その決定を下した裁判長は鬼丸かおる。弁護士出身の裁判官である。
日本は「子どもの拉致国家」
国際的には、日本は「子どもの拉致国家」であり、その元凶が司法にあるとの認識が定着しつつある。
米連邦捜査局(FBI)の最重要指名手配犯リストでは、米国人の元夫に無断で子どもを連れて日本に帰国した日本人女性の名前が、テロリストと同様に扱われている。
米国ではこの10年近く、議会において何度も公聴会が開催され、日本の司法がこのような「実子誘拐犯」の引き渡しに応じないだけでなく、「誘拐犯」に親権を与えるなどの行為を行うことで「実子誘拐」を助長している、と繰り返し非難している。
また、米国務省は、2018年に出した「国際的な子どもの拉致」年次報告書で、日本を国際的な子どもの誘拐を禁ずる「ハーグ条約」の不遵守国と認定した。
同年3月には、26人のEU加盟国大使が、親に会う子どもの権利を尊重するよう日本に訴えかける文書を出した。昨年6月にはフランスのマクロン大統領が安倍首相に、「実子誘拐」について問題提起したうえで、「容認できない」と言及した。
イタリアのコンテ首相もまた、同月に開催されたG20のグループ会議で、子どもに対する両親の権利について安倍首相に懸念を表明した。
今年の1月に、オーストラリア政府が日本の法務省に対し、家族法を改めるよう要請したとの報道もある。
これだけ諸外国政府から非難されている背景には、日本人による「実子誘拐」と日本の司法の実態が繰り返し海外で報道され、対日感情が悪化している背景がある。
「日本の司法システムを批判する論調が支配的なフランスでは、ゴーン前会長の逃亡容認論が根強い。仏紙フィガロが『ゴーン氏が日本から逃げ出したのは正しかったか』と読者に尋ねたところ、正しかったと応じた人が77%に上った」
と伝える記事を最近見かけたが、フランスにおいて日本の司法システムを批判する論調が支配的となってしまった原因の一つに、「実子誘拐」の問題があると考えられる。
この松戸判決が東京高裁で覆されることがなく最高裁で確定していれば、あるいは最高裁が東京高裁の判決を覆していれば、日本で「実子誘拐ビジネス」はできなくなり、現在、ここまで諸外国から批判を受けることもなかったはずである。
一刻も早く、この悪名高い「継続性の原則」をやめさせ、裁判所を子どもの利益を第一に考える場にしなくてはならない。
しかし、なぜこれほど外国から批判される「実子誘拐」が日本で社会問題とならないのであろうか。その理由は、A氏のケースを見ることでよく分かる。
でっちあげDVで人格攻撃
嘘も100回言えば本当になる……?
A氏のケースに戻る。裁判所の従来の慣例を覆す一審判決の直後から、被告39人のA氏に対する執拗かつしたたかな人格攻撃が展開された。以下、A氏が今回提訴した名誉毀損行為の数々だ。
◇NPO法人全国女性シェルターネットの理事(元代表)である被告近藤恵子が講師を務める内閣府主催のDV相談員研修会において、同法人の共同代表である被告北仲千里、被告土方聖子が、研修会の参加者に対して、A氏がDVを行う人物であると印象づけるビラを作成して配布し、一審判決を見直すよう高裁へ要望する書面への署名を求めた。
この問題は、衆議院予算委員会・法務委員会でもとりあげられ、内閣府男女共同参画担当大臣から当該行為に対し、「のぞましくない」との答弁がなされている。なお、被告北仲はこの事件が国会で糾弾されたにもかかわらず、内閣府主催「DV等の被害者のための民間シェルター等に対する支援の在り方に関する検討会」の構成員に選ばれている。
◇被告近藤恵子は、一審判決に関して産経新聞から取材を受けた際に、「DVは冤罪というのは加害者の論理だ。支援に当たったケースで冤罪DVはゼロ。今回の事例でも、私たちは夫にDVに当たる行為があったと考えている」「母親が不当に子どもを連れ去ったのではなく、実態はDVから自身と子どもを守るための緊急避難だった」などと話した。
そのため、A氏が実際はDVを行っていたかのような印象を与える記事となって報道されることとなった。なお、被告近藤は以前、朝日新聞からの取材に対し、「被害者が(シェルターに)逃げている事実が、DVの明確な証拠」と主張している。
◇妻側の弁護団を構成する被告蒲田孝代、清田乃り子、齋藤秀樹、坂下裕一、本田正男ら総勢31人は、二審東京高裁判決後に司法記者クラブで開いた記者会見において、「弁護団作成資料」と称するものをメディア関係者に配布した。
その資料には、A氏が「大声で怒鳴る、食器を投げつける、はさみを突き付けるなどとしたためA氏の妻は子どもを連れて逃げたのだ」などと記載されており、「実子誘拐」を正当化する内容のものであった。この記者会見を受け、「妻側が夫のDVを主張している」とテレビのニュースでも報道された。
なお、被告の弁護士らの大半は「人権派」弁護士と称される者たちである。特に、妻側弁護団の主任弁護士の被告蒲田孝代は、千葉県弁護士会会長や日弁連理事を歴任した大物「人権派」弁護士である。
「人権派」たちの裏の顔
言っていることと、やっていることが正反対!
◇NPO法人の代表理事であるほか、「イクメン(育MEN)プロジェクト推進委員会」(厚生労働省主管)、「子ども・子育て会議」(内閣府主管)および「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」(内閣府主管)の委員ないしメンバーであり、かつ、日弁連の市民会議委員である被告駒崎弘樹は、二審判決が出された当日、ツイッター上(フォロワー数が数万人)で「モラハラ夫(父)に引き渡すわけないだろう。少し裁判調べれば分かることだ」など、裁判では全く認められていないことをあたかも裁判で認められたかのように印象付ける虚偽の内容を流布した。
◇フェミニズムを専門とする大学教授の被告千田有紀は連合会館において、A氏の妻がA氏の暴力が原因で「実子誘拐」をしたのだと印象付ける講演を行った。
なお、被告千田と被告駒崎は、「実子誘拐」の被害者である親には人格に問題があるかのような印象を与えるプロパガンダ記事をネット上に次々と配信している。たとえば、「実子誘拐」の被害者である父親を誹謗中傷する記述の隣にナイフを持った男の写真を置くことで、あたかも「実子誘拐」の被害者が殺人犯と同等の加害者であるかのようなイメージを読者に抱かせる効果を狙うなど、その手法は非常に洗練されている。
◇朝日新聞の論壇委員(当時)を務めていた被告木村草太は、被告蒲田が投稿した法学セミナー記事を朝日新聞紙面で「論壇委員が選ぶ今月の3点」として取り上げ、「離婚後の面会交流のあるべき形や『フレンドリーペアレント・ルール』の弊害など、多くを学ぶことができる論稿である」と記載した。
さらに、NPO法人代表であり朝日新聞の論壇委員(当時)であった被告赤石千衣子は、被告木村の記事をツイッター上で再引用して「重要」と付け加えるなどし、A氏による暴力があったとする主張を拡散した。
この被告蒲田の記事については、中立的立場にある弁護士がブログで「蒲田弁護士は、当事者である原告(A氏)を『人格攻撃』しているが、理屈で責められないということは論理破綻していることの証左である」「蒲田弁護士の一方的な罵詈雑言の類が書いてあるに過ぎない」と痛烈に批判しているように、この記事自体が名誉毀損の対象となる代物である。
にもかかわらず、被告木村と被告赤石は、この記事を手放しで賛美しているのである。その裏には強いつながりがあると考えるのが自然である。
そのつながりを示す一例として、本年1月27日、被告赤石がシングルマザーサポート団体全国協議会代表として、被告駒崎らとともに「養育費の取り立て確保に関する要望」を法務大臣に提出した事実が挙げられる。
要望書には「養育費差押えの支援」のほか、「共同親権制度など親権の在り方とはリンクさせないこと」などの記載もある。この文書からは、子どもを奪われて会うこともできずに苦しんでいる親から金を奪いとることへの良心の呵責は微塵も感じられない。
被告駒崎は、昨年12月「第三文明」において「子どもの権利を阻害する離婚後共同親権」との見出しをつけ自説を展開したうえで、「公明党と共に頑張っていきたい」と結んでいる。
この自説が全くの虚偽であることは、昨年の2月に国連子どもの権利委員会が「子どもの権利条約の実施状況」の対日審査結果を公表し、「子どもの共同親権を認める目的で、離婚後の親子関係について定めた法律を改正するとともに、非同居親との個人的関係および直接の接触を維持する子どもの権利が恒常的に行使できることを確保すること」と、日本政府に勧告した内容に矛盾することからも明らかである。
また、被告木村は、離婚後に両方の親が親権を共同して行使する共同親権制度導入に反対し、虚偽を流布している。
たとえばその著書において、1982年にドイツ憲法裁判所が出した判決を援用し、「日本の離婚後の単独親権の規定は合理性がある」と主張している。しかし当該判決こそ、民法に規定する離婚後の単独親権制度が違憲であると判示し、離婚後の共同親権制度改正の立法化につながった画期的な判決なのである。
その判決をあたかも単独親権を支持する判決であるかのように読者に紹介して印象操作するやり方は、今回のA氏に対する名誉毀損の手口に通ずるものがある。
◇被告には元裁判官の浅田登美子と若林辰繁が含まれている。被告若林は、あろうことかA氏の事件を担当した裁判官であり、A氏を敗訴させる審判書を書いた者である。若林はA氏を敗訴させたあと、A氏の妻の代理人である被告坂下のいる弁護士事務所へ天下った。なお、若林は「『継続性の原則』があるから連れ去ったほうが得だということがあってはならない」などの法務大臣発言に対し、「法務大臣が何を言おうが関係ない」と言い放ったと報じられている人物である。
大衆操作で「人格破壊」
このように、A氏への人格攻撃は様々な場所で同時多発的に展開された。見事な連携プレーである。
訴状では、「被告はA氏が一審で勝訴した結果に脅威を覚え、先例として最高裁判所にて確定しないよう、また、親による子の連れ去りや引き離し行為を禁ずる方向に世論が向かないよう、A氏の評価を集団で徹底的におとしめ、社会から抹殺しようとしたのだ」と主張する。
「このような行為は、欧米では『人格破壊(Character Assassination)』と呼ばれ、大衆操作の一手法として知られる。相手の主張や行為そのものを攻撃するのではなく、組織的に計画的にメディアなどを使って大衆を操作し、相手の社会的評価やイメージを著しく下げることで、その影響力を無力化させるのである」とも主張している。
A氏がDV行為を行っていた証拠はどこにもない。松戸判決において、「(A氏の妻はA氏に対して)身体的・経済的・精神的・性的暴力を婚姻破綻の原因及び慰謝料の発生原因として主張するが、そのような事実を認めるに足りる証拠はない」と断じている。
判決文でここまで踏み込んで記載することは異例である。担当裁判官が「DVが全くなかった」と確信していない限り、ここまでの言葉は書けない。A氏の妻の主張には根拠が全くなかったのだ、と推認される。
しかしそのような判決内容は、39人もの社会的影響力や信用力のある者が同時多発的に虚偽を流布すれば、完全に上書きできるのである。
さらに、訴状や提出された証拠資料などを見ると、A氏の妻と被告らは共謀し、「A氏の妻や被告らが行った実子誘拐行為や、それを正当化するために虚偽のDVを捏造した行為」を報道する記事を見つけると、裁判をするぞなどと、記事を書いた記者やライター、編集部に圧力をかけ、記事をネット上から落とさせたりさせるなどの工作を行っていたことも分かっている。
これは表現の自由を侵害する行為であり、憲法の規定に違反する重大な人権侵害行為であるが、これを憲法学者を自称する木村草太や「人権派」と称される弁護士たちが行っているのは皮肉である。
被告らの工作はこれまで成功しており、一般の人の目に見えるのは、被告らにとって都合の良い記事ばかりである。「噓も100回言えば本当になる」との慣用句があるが、この39人こそ、その言葉が真実であると実感していることであろう。
「実子誘拐」ゼロ社会へ
いまの日本では「実子誘拐」が毎日のように行われ、それを正当化するために虚偽のDVが捏造されている。「実子誘拐」を遂行する者たちにより、子どもを誘拐された親は、さらにDV夫・虐待母の烙印まで押されるのである。その無法な状況を社会に告発しようとするメディアは少ない。
A氏の訴訟は、この状況を打開する一筋の光である。
判決を書くことになるのは被告の同業者である裁判官であり、まともな判決が出る可能性は少ないのかもしれない。しかし、裁判所のなかにも松戸判決の担当裁判官のように人間的な良心を持つ裁判官もいる。大岡越前の名裁きで事態が変わることを期待したい。
A氏は、今年3月10日から始まる今回の民事訴訟に加え、親権者変更の申立てをする予定であるとのことである。松戸判決が二審で覆された結果に絶望し、自殺した父親もいたことを聞き、自分や自分の娘のためだけでなく、この国で「実子誘拐」の被害に遭い苦しんでいる親子のためにも諦めてはならないと考え、その決意を固めたという。
子どもが両親の離婚後も両方の親と自然に会うことができる仕組みは、松戸判決で提示された「フレンドリーペアレント・ルール」を導入することで保障される。これが最高裁で採用されれば、日本社会は大きく変わるはずである。
この問題は、日本社会の根幹にかかわる家族の問題であり、三権の一角を占める司法の在り方にかかわる問題であり、全ての人に関係のある問題である。誰もが明日、自分の子どもや孫が連れ去られ、その1年後に裁判所で「自殺するなら敷地の外でしろ」と嘲笑される立場に陥っているかもしれないのである。
是非、多くの人々が自分のこととして真摯に考えてほしい。ともに立ち上がってほしい。いまこそ、まっとうな正義を取り戻し、親子が引き裂かれない社会を現実とする時である。
(文中敬称略)
(初出:月刊『Hanada』2020年5月号)

月刊『Hanada』2020年5月初夏号(Kindle版)
¥ 855